生成AIを学び仕事に活かすオンラインスクール「DMM 生成AI CAMP」
生成AIを活用できる人材の需要は急拡大。生成AIを学ぶなら「DMM 生成AI CAMP」がおすすめ!
- 生成AIの事前知識が全くない方でもOK!
- 現場で使えるスキルが短期間で身につく
- 無制限のチャットでの質問で「わかる」までサポート
- 無料相談に参加で特典あり!
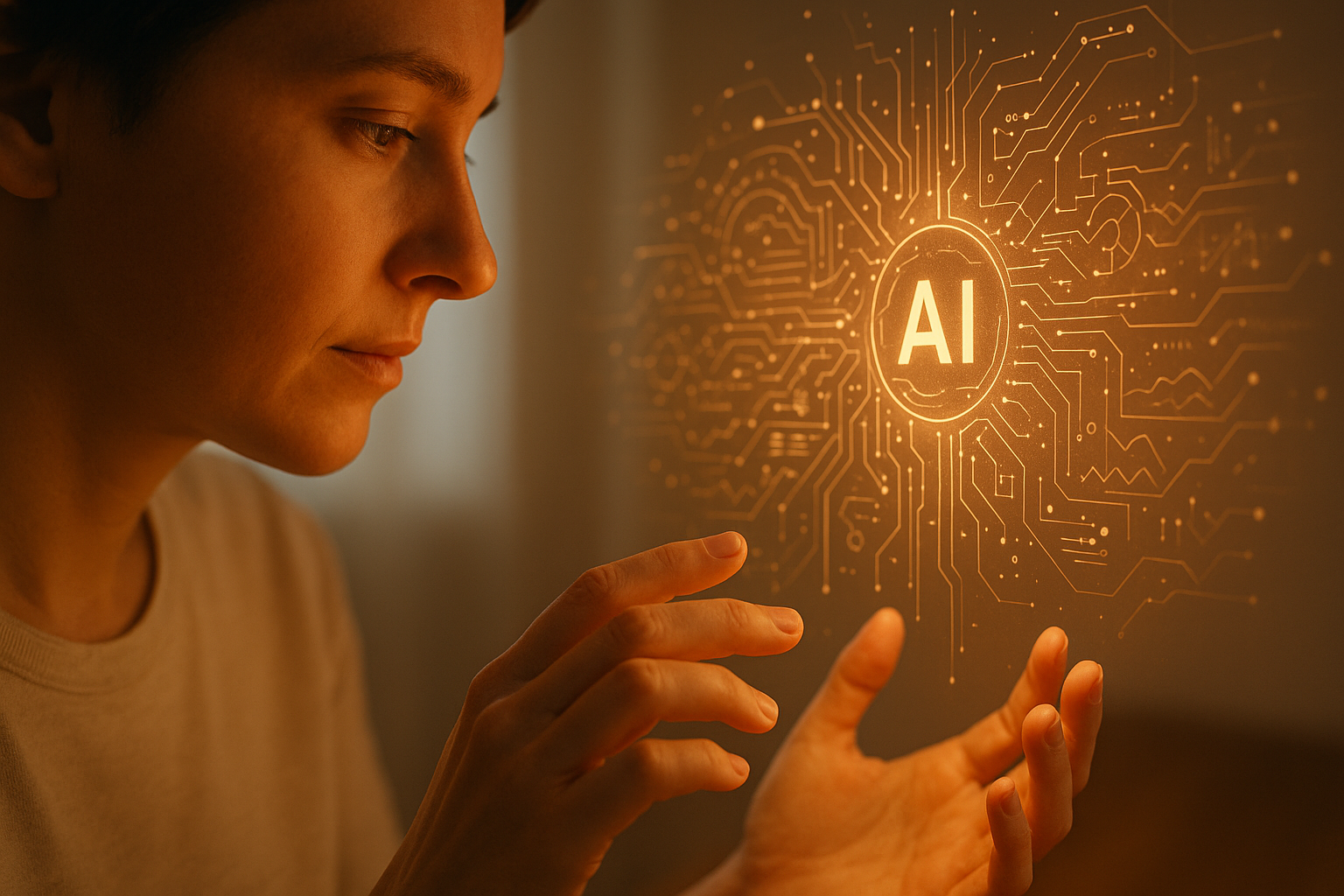
生成AIを学び仕事に活かすオンラインスクール「DMM 生成AI CAMP」
生成AIを活用できる人材の需要は急拡大。生成AIを学ぶなら「DMM 生成AI CAMP」がおすすめ!
Midjourneyは非常に便利な画像生成AIですが、利用するうえで知っておくべき危険性も存在します。特に注意したいのが、著作権侵害、情報漏洩、悪用、そして倫理的な問題の4つです。
これらのリスクを理解しないまま利用すると、思わぬトラブルに巻き込まれかねません。この記事では、それぞれの危険性の詳細と、安全に利用するための具体的な対策を解説していきます。
Midjourneyが抱える大きなリスクの一つが、著作権侵害の可能性です。Midjourneyはインターネット上の膨大な画像を学習しているため、その中には著作権で保護されたアート作品や写真も含まれている可能性があります。
そのため、生成された画像が既存の作品と偶然似てしまい、著作権侵害を指摘されるケースが考えられます。特に、実在するアーティストのスタイルを模倣するようなプロンプト(呪文)を入力した場合、そのリスクはさらに高まります。
Midjourneyはコミュニケーションアプリ「Discord」上で操作するため、情報漏洩のリスクにも注意が必要です。基本設定では、あなた自身が入力したプロンプトや生成した画像は、サーバー内の他のユーザーも閲覧できる状態で公開されます。
もし、プロンプトの中に個人情報や企業の機密情報などを入力してしまうと、それが不特定多数に知られてしまうおそれがあります。プライベートな内容や、仕事で使う画像を生成する際には特に注意が必要です。
Midjourneyの性能の高さは、裏を返せば、悪用される危険性も高まることを意味します。特に懸念されているのが、実在の人物の偽画像を生成する「ディープフェイク」です。
有名人や政治家が過激な発言をしているかのような偽画像が作られ、SNSで拡散されるといった事件も実際に起きています。こうしたフェイクニュースは、社会に混乱を招き、個人の名誉を著しく傷つける危険な行為です。
AIは学習したデータに基づいて画像を生成するため、そのデータに含まれる社会的な偏見(バイアス)を反映してしまうことがあります。例えば、特定の職業を特定の性別や人種のイメージで描き出すなど、意図せず差別的な表現を生み出してしまう可能性があるのです。
また、Midjourneyでは暴力的なコンテンツや成人向けコンテンツの生成は利用規約で禁止されています。しかし、プロンプトの解釈によっては、倫理的に問題のある不適切な画像が生成されるリスクも考慮しなければなりません。
これまで解説してきた危険性は、決して机上の空論ではありません。実際にMidjourneyに関連して起きた具体的な事例を知ることで、リスクをより身近な問題として捉えられるでしょう。
ここでは、著作権、ディープフェイク、情報漏洩という3つの観点から、象徴的な事例をそれぞれご紹介します。
2023年1月、アメリカで複数のアーティストがMidjourneyや他の画像生成AI企業を相手取り、集団訴訟を起こしました。これは、AIの学習プロセスそのものを問う画期的な出来事です。
アーティストたちの主張は、「自分たちの作品が無断でAIの学習データに使われたことで、著作権が侵害された」というものです。この裁判の行方は、今後の画像生成AIとクリエイターの関係性を大きく左右するものとして、世界中から注目を集めています。
Midjourneyの悪用例として特に有名なのが、政治家の偽画像(ディープフェイク)がSNSで拡散した問題です。例えば、アメリカのトランプ前大統領が逮捕される瞬間の画像や、フランスのマクロン大統領がデモの真っ只中にいる画像などが生成され、大きな騒ぎとなりました。
これらの画像は非常にリアルで、多くの人が本物だと信じてしまうほどでした。このように、Midjourneyが悪意を持って使われると、世論を操作したり、社会不安を煽ったりする強力なツールになり得ることを示した事例です。
これは特定の事件ではありませんが、Midjourneyの仕様そのものに起因する日常に潜むリスクです。前述の通り、Midjourneyでは基本的に自分のプロンプトや生成画像が他のユーザーに公開されます。
「すごいプロンプトを思いついた!」と思っても、それが他の人に丸見えになってしまい、アイデアを模倣される可能性があります。特に、ビジネスで利用する際には、未公開のデザイン案などが外部に漏れてしまう致命的なリスクになり得ます。
ここまでMidjourneyの危険性について解説してきましたが、もちろん、対策を講じれば安全に利用できます。少し意識を変えるだけで、多くのリスクは回避可能です。
ここでは、今日から実践できる具体的な5つの対策をご紹介します。これらを習慣づけて、安心してMidjourneyを楽しみましょう。
最も基本的で重要な対策は、Midjourneyが定める公式ルールを守ることです。利用規約やコミュニティガイドラインには、どのような画像の生成が禁止されているか(例:暴力的、差別的な内容など)が具体的に記載されています。
これらのルールは、ユーザー全員が安全で快適にサービスを利用するために設けられています。利用を開始する前に一度は目を通し、禁止事項を正しく理解しておくことが、トラブルを未然に防ぐための第一歩です。
著作権侵害のリスクを避けるためには、プロンプトの入力内容に注意を払う必要があります。特に、実在するアーティストやキャラクター、ブランド名などを直接プロンプトに含めるとリスクが非常に高まります。
「〇〇先生風のイラスト」といった指示は、意図せず他者の権利を侵害する可能性があります。具体的な固有名詞を使うのではなく、「鮮やかな色彩の水彩画」のように、一般的な表現でイメージを伝える工夫をしましょう。
情報漏洩のリスクに対する最もシンプルで効果的な対策は、「重要な情報を入力しない」ことです。これはMidjourneyに限らず、あらゆるオンラインサービスに共通する鉄則です。
氏名や住所といった個人情報は絶対にプロンプトに含めないでください。また、ビジネスで利用する場合も、社外秘のプロジェクト名や製品情報などを入力するのは厳禁です。公開されても問題ない情報だけで画像を生成するよう徹底しましょう。
どうしても他人に作業内容を見られたくない場合は、有料プランの「ステルスモード」を利用するのが有効な解決策です。この機能を使えば、自分のプロンプトや生成画像を非公開に設定できます。
ステルスモードは、ProプランまたはMegaプランに加入することで利用可能になります。企業の業務利用や、コンペ用の作品制作など、機密性を確保したい場合には必須の機能と言えます。情報漏洩対策として最も確実な方法です。
画像を生成した後にも、やるべき対策があります。それは、完成した画像を公開する前に、既存の作品と似すぎていないかを確認する一手間です。Googleの画像検索などを使えば、似たような画像がネット上にないか簡単にチェックできます。
また、人物などのリアルな画像を生成した場合は、それが誰かの肖像権を侵害したり、フェイクニュースとして誤解されたりする可能性がないか、公開前に一度立ち止まって考える習慣をつけましょう。
Midjourneyをビジネスで活用したいと考えている方にとって、商用利用と著作権のルールは避けて通れない重要なテーマです。規約を正しく理解していないと、後々、大きなトラブルに発展しかねません。
ここでは、Midjourneyの利用規約の中から、特に商用利用に関わる著作権のポイントを分かりやすく解説します。
Midjourneyの利用規約では、有料プランに加入しているユーザーが、生成した画像の所有権を持つと定められています。つまり、基本的にはあなたが生成した画像の権利はあなたのものになる、ということです。
ただし、これには例外と注意点があります。まず、無料ユーザーが生成した画像の権利はMidjourney側に帰属します。また、たとえ有料ユーザーであっても、Midjourney側はサービス運営や宣伝のためにあなたの画像を利用する権利を持っています。さらに、AI生成物の著作権は法的にグレーな部分も多く、今後の判例次第で扱いが変わる可能性も認識しておく必要があります。
Midjourneyで生成した画像を広告や商品デザインなどに使って利益を得たい場合、必ず有料プランに加入しなければなりません。これは利用規約で明確に定められている、最も重要なルールです。
無料プラン(現在は停止中)で生成した画像を使ってしまうと、規約違反となります。ビジネスでMidjourneyを活用するなら、まずは最も手頃なプランからでもよいので、有料サブスクリプションに登録することが大前提となります。
個人や小規模なビジネスとは別に、大企業向けの特別なルールも存在します。会社の年間総売上が100万ドルを超える場合、BasicプランやStandardプランでは商用利用が認められていません。
該当する企業は、より上位のProプランまたはMegaプランへの加入が必須となります。これは、企業の規模に応じた適切なライセンス契約を求めるための規定です。自社の売上規模を確認し、適切なプランを選択するようにしましょう。
企業としてMidjourneyを本格的に導入する場合、個人の利用とは比較にならないほど厳格な管理体制が求められます。安易な導入は、企業の信用を揺るがす大きなリスクにつながりかねません。
特に以下の点に注意し、社内ルールを整備することが不可欠です。
Midjourneyを安全かつ有効に活用するためには、自分に合った料金プランを選ぶことが大切です。各プランの料金と主な特徴を比較してみましょう。
ここでは、代表的な4つのプランをご紹介します。なお、料金は変動する可能性があるため、契約前には必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。
| プラン名 | 月額料金(月払い) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Basic | $10 | お試し向け。月におよそ200枚の画像を生成可能。 |
| Standard | $30 | 個人利用のスタンダード。リラックスモードで画像を無制限に生成可能。 |
| Pro | $60 | ステルスモードが利用可能。ビジネス・法人利用の最低ライン。 |
| Mega | $120 | ヘビーユーザー・大規模法人向け。高速生成時間が最も長い。 |
月額10ドルから始められる最も手頃なプランです。「まずはMidjourneyがどんなものか試してみたい」という方に最適です。
月に約200枚程度の画像を高速で生成できますが、生成時間を使い切ると追加の生成はできなくなります。商用利用は可能ですが、あくまで個人のお試し用と位置づけるのがよいでしょう。
月額30ドルのStandardプランは、多くの個人クリエイターにとって最もコストパフォーマンスが高い選択肢です。高速な画像生成時間が月に15時間分と大幅に増えます。
このプランの最大の魅力は、高速生成時間を使い切っても、低速の「リラックスモード」で画像を無制限に生成し続けられる点です。枚数を気にせず、とことん画像生成に没頭したい方におすすめのプランです。
Proプラン(月額60ドル)とMegaプラン(月額120ドル)は、プロフェッショナルや法人向けの最上位プランです。これらのプランの最大のメリットは、情報漏洩を防ぐ「ステルスモード」が使えることです。
前述の通り、年間売上が100万ドルを超える企業はこちらのプランへの加入が必須です。高速な生成時間も非常に長く確保されており、大量の画像を効率的に制作する必要があるヘビーユーザーや、セキュリティを重視するビジネスシーンには不可欠なプランです。
最後に、Midjourneyの危険性や利用ルールに関して、特に多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。
現在、Midjourneyを無料で継続的に利用する方法はありません。以前は新規ユーザー向けに無料トライアルが提供されていましたが、悪用問題などを受けて2023年3月頃に停止されています。
Midjourneyの全ての機能を利用するには、いずれかの有料プランに登録する必要があります。特別なキャンペーン期間などを除き、基本的には有料サービスであると理解しておきましょう。
はい、有料プランに加入していれば、生成した画像をSNSに投稿することは問題ありません。利用規約上、画像の所有権はあなたにあるため、自由に公開できます。
ただし、投稿する際には注意が必要です。生成した画像が、特定のキャラクターや実在の人物にそっくりで、権利侵害の可能性がある場合は、トラブルを避けるためにも投稿は控えるのが賢明です。常識の範囲内で楽しむようにしましょう。
この記事では、Midjourneyに潜む危険性と、それらを回避するための具体的な対策について詳しく解説しました。
Midjourneyは、私たちの創造性を飛躍的に高めてくれる画期的なツールです。しかし、その裏には著作権侵害や情報漏洩といった、見過ごせないリスクも存在します。重要なのは、これらの危険性を正しく理解し、適切な対策を講じながら利用することです。
利用規約を守り、他者の権利を尊重する姿勢を忘れずに、あなたの創作活動やビジネスの強力な味方として、Midjourneyを活用していきましょう。
生成AIを学び仕事に活かすオンラインスクール「DMM 生成AI CAMP」
生成AIを活用できる人材の需要は急拡大。生成AIを学ぶなら「DMM 生成AI CAMP」がおすすめ!